(高田宏臣寄稿)奥秩父のとある山中に残る導水路より
(有機土木協会代表理事 高田宏臣のFacebookページより転載)
先週訪ねた奥秩父のとある山中に残る導水路。

昭和初期と思われる。岩盤からの湧水を集め、そして余水は沢に戻る。湧水を妨げず、そのため山を痛めず、必要以上の水は川に戻り、水は清く冷たい。
山河を痛めず、必要な水をいただく造作は半世紀以上の時を経て機能し、美しく神々しく、山々もこの人間の造作を受け入れている。
かつてのそれとは対比的に、戦後のダム開発の中で埋め込まれた閉鎖的な導水路は今、あちこちで大規模な土砂崩壊の原因となるケースが多い。
自然に逆らい続けてきた現代土木がつくってしまった矛盾だらけのインフラが今、社会基盤を根底から揺るがす膨大な負の遺産となりつつある。
故郷を愛おしみ、その恵みの源である健康な山河を守り、そしてその恵みを独占しようとせず、全ての命と共にあろうとした先人たちの残した美しきインフラ、美しき造作が今、未来への道しるべとなる。
山が乾けば山の動物たちは生きられず、里に降りてくる。
また、クマさんのような賢い動物たちは、人間が何をしているか。、分かっている。それがいのちの法則に従うものか、そうでないものか。
今、クマの恐怖を煽り立てる前に、里山における人間の営みが他の生きものたちにとって暮らしやすいものにしてきた矛盾なき生き方や技を今、掘り起こし、伝えたい。





関連エントリー
-
 (会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。
高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神
(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。
高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神
-
 (会員寄稿)建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポート(2025年12月20日開催)
建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポートパッシブデザインプラス
(会員寄稿)建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポート(2025年12月20日開催)
建築 + 土中環境 / 「学校の先生とつくる家」有機土木 施工会 第一期レポートパッシブデザインプラス
-
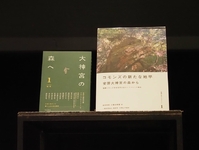 (会員寄稿)『大神宮の森へ』& 『有機土木ライブラリー』創刊記念トークイベントが開催されました。
12/26、紀伊國屋書店新宿本店にて、
『大神宮の森へ』および「有機土木ライブラリー」創刊を記念したトークイベ
(会員寄稿)『大神宮の森へ』& 『有機土木ライブラリー』創刊記念トークイベントが開催されました。
12/26、紀伊國屋書店新宿本店にて、
『大神宮の森へ』および「有機土木ライブラリー」創刊を記念したトークイベ
-
 (会員寄稿)安房大神宮の森整備報告(2025年12月)
今日は今回安房大神宮の報告書を手がけることになりました高田造園で勉強させていただいている林大介です。よろしくお
(会員寄稿)安房大神宮の森整備報告(2025年12月)
今日は今回安房大神宮の報告書を手がけることになりました高田造園で勉強させていただいている林大介です。よろしくお
-
 (会員寄稿)氷川神社参道の杜の環境再生を行いました。(2026年1月16日)
高田造園で勉強させていただいております大澤です。埼玉県さいたま市の武蔵一宮氷川神社の参道にて、杜の環境再生が行
(会員寄稿)氷川神社参道の杜の環境再生を行いました。(2026年1月16日)
高田造園で勉強させていただいております大澤です。埼玉県さいたま市の武蔵一宮氷川神社の参道にて、杜の環境再生が行
