【イベント案内】7月25日開催 生きものとしての土木研究会オンライン学習会第5回 都市型水害対策と雨庭
2025/07/11
7月のオンライン学習のお知らせです。
2025年7月25日、『生きものとしての土木研究会オンライン学習会第5回「都市型水害対策と雨庭~これからのグリーンインフラを考える~ 」をpeatixにて開催いたします!
近年、自然を活かしたインフラ整備(グリーンインフラ)の一つとして広まりつつある「雨庭」。
雨庭は“地上に降った雨水を下水道に直接放流することなく一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透させる構造を持った植栽空間”と国交省は定義しており、気候変動による防災、減災の観点から、個人邸にとどまらず、各自治体でも雨庭の観点を用いた施工が実施されています。
緑が急激に減少し、水害が日常的に脅威となっている都市空間において、『雨庭』が普及していくことは一つの希望と言えるでしょう。
ただ、雨水を一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透させる構造として、雨庭と称した様々な施工方法が実施されており、施工方法によっては、期待している効果が永続的に得られず、最悪の場合、逆にその土地の環境を悪化させてしまう、と有機土木協会代表理事の高田宏臣は懸念しています。
時が経てば経つほどその土地の環境を豊かにしていくことで、その機能をさらに向上させていくのが、本来の100年続いている伝統的な雨庭です。
今回のオンライン学習会では、そんな雨庭について、過去には古庭園の調査を行い、日頃は土中の水と空気と有機物が循環することを目指してその土地の環境と向き合っている高田が、様々な観点から報告・解説いたします。
さらに今回は、第4回グリーンインフラ大賞特別優秀賞を受賞した埼玉県川越市の個人邸の雨庭を設計施工(監修:高田宏臣)された有限会社栗原造園の栗原薫さん、雨庭の雨水貯留浸透能力の経年変化について研究を進めておられる建築設計事務所パッシブデザインプラス株式会社の冨田ご夫妻にも報告を行っていただきます。
そして後半は、上述の報告者と、グリーンインフラ普及を目指す市民団体の設立メンバーであるお庭屋さんほうきの法貴弥貴さんにも加わっていただき、参加者の皆様の質問にお答えしながら、雨庭について深く掘り下げていきます。
《高田宏臣よりメッセージ》

この写真は明治初期、街道沿いの宿場町です。道の中央に素掘りの水路があり、豊富な清水の流れが見られます。
家屋への往来は、軒下の素掘り溝に架かる石橋を渡ります。
古来、土地を刻み、町を整備する際、それは常に掘と池の配置と掘削から始まります。
それこそが、古今東西当たり前に行われてきた、洪水を緩和すると同時に流されにくいレジリエントな大地を保つための治水のための造作であったのでした。
水の道を想定し、自然に従って作られるその光景は美しく、水路際の木々は清冽な地下水を得て大木に育ちます。
また、冷涼な水路の流れは夏に涼風をもたらし、町全体を快適で潤い豊かにしてきたのでした。
街道には水路、そして家の中庭や山際には治水のための池を掘り、そして池から溝を掘って水の動きを作ることで大地の貯水機能を育み、大雨に備えてきたというのが、かつてのインフラ整備であったのです。

昨今、「グリーンインフラ」や「雨庭」という言葉が、にわかに注目されています。しかしそれはかつて、安全で暮らしやすい住まいの環境を守るために誰もが当たり前に行ってきた日常造作であったのでした。
池を掘り、溝を切り、そして木を植えてきた、そんな先人の営みがもともとあったことを今、思い起こす必要がありましょう。
江戸時代、東海地方の農民たち技術を伝えた書籍、百姓伝記(底本;推定江戸期)の第7巻防水集の記述の中に「雨池・堀・堤普請心得の事」との章があります。
その記述から、池や溝の掘削が大切な治水のための造作であることの認識が理解されていたことがうかがえます。
注目すべきは、雨池という言葉が江戸時代にすでに定着していた点であります。「雨庭」という言葉は決して新しい概念ではなく、近代化の中で一度は捨て去ってしまった、伝統に裏打ちされた技術と認識に、現代社会がようやく追いついてきた証とも言えるのではないでしょうか。
百姓伝記防水集に、治水は農耕の始まった古い時代から今日に至るまで百姓の義務とされてきたことも記されています。
市民住民による治水と大地の涵養、これこそが、現代にわかに注目される、グリーンインフラの目指すものであり、それは先人が積み重ねてきた知恵と技への回帰に他ならないことでしょう。
今、ハードインフラを偏重した人工的な都市型水害対策の限界に直面している私たちは、大地本来の治水機能をどう活かしてゆくかというのが、グリーンインフラに着目する発想の根本にあります。
そしてそれが市民一人一人の認識と努力を必要とすることもまた、現代の行動の新たな方向性の一つです。
安全で豊かな暮らしの環境は、地域に暮らす人たちが自ら手で行うという、本来の在り方への回帰であります。
それは現代社会が求めてきた、河川整備や治水治山のためのダム建設、巨大な地下排水設備建設などといった大規模土木を伴うものとはある意味対極にあるものです。
今回の学習会では、小さな溝や池で大きな治水機能を作り上げてきたかつての知恵と技を紹介いたします。その技術復権が土地環境の再生にもつながるよう、学びを深める機会になればと思います。
現代の雨水浸透とかつてのそれとの視点の違い、そして。大地の涵養機能の変化の予測・測定についての最新の試みなど、ここで紹介していきたいと思います。
とても貴重な機会ですので、多くの方のご参加を心よりお待ちしております。
有機土木協会代表理事 高田宏臣
〈学習会概要〉
スピーカー
高田宏臣(有機土木協会代表理事)
ゲスト
栗原薫(有限会社栗原造園)
冨田享祐、冨田倫世(パッシブデザインプラス株式会社)
法貴弥貴(お庭屋さんほうき)
司会
堀越侑莉奈(株式会社高田造園設計事務所)
日時
2025年7月25日金曜日 19:30~21:15
スケジュール
19:30 開始、導入
19:35~20:35 雨庭についての解説&報告
・基調報告・解説(高田宏臣)
・雨庭の科学的検証について(冨田享祐さん、冨田倫世さん)
・埼玉県川越市個人邸での施工について(栗原薫さん)
20:35~21:00 質疑応答&ディスカッション
(高田、冨田ご夫妻、栗原さん、法貴弥貴さん)
21:00~21:15 お知らせ、終わりのあいさつ
参加方法
Peatixより申し込みください。
Peatixで申し込み完了いたしますと、ページでリンクが取得できます。
※申し込めない場合は、下記メールアドレスまでご連絡ください。
mgmt@organiccivilengineering.org
アーカイブ
今回も学習会に申し込んでくださった方々に後日アーカイブをお送りいたします。
お願い
学習会についてのご質問は、Peatixイベントページの、「主催者への問い合わせ」からお寄せくださいますようお願い致します。
*内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
ここまでお読みくださいましてありがとうございます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
-
 【イベント案内】12月20日開催 パッシブデザインプラス株式会社 有機土木施工会
当協会でも協働の多いパッシブデザインプラス株式会社さまで有機土木施工会が開催されます。土地に新たに家を建てる時
【イベント案内】12月20日開催 パッシブデザインプラス株式会社 有機土木施工会
当協会でも協働の多いパッシブデザインプラス株式会社さまで有機土木施工会が開催されます。土地に新たに家を建てる時
-
 【オンライン学習会のご案内】12月28日開催 生きものとしての土木研究会学習会第9回『建築と有機土木 インフラ崩壊の時代の新たな土木を目指して』
12月28日、いよいよ今年最後の生きものとしての土木研究会となります。この学習会は、土地を傷めることなく育む古
【オンライン学習会のご案内】12月28日開催 生きものとしての土木研究会学習会第9回『建築と有機土木 インフラ崩壊の時代の新たな土木を目指して』
12月28日、いよいよ今年最後の生きものとしての土木研究会となります。この学習会は、土地を傷めることなく育む古
-
 【イベント報告】12月28日開催 生きものとしての土木研究会学習会第9回『建築と有機土木 インフラ崩壊の時代の新たな土木を目指して』
12月28日、「生きものとしての土木研究会」オンライン学習会の第9回を開催しました。2025年の有機土木施工の
【イベント報告】12月28日開催 生きものとしての土木研究会学習会第9回『建築と有機土木 インフラ崩壊の時代の新たな土木を目指して』
12月28日、「生きものとしての土木研究会」オンライン学習会の第9回を開催しました。2025年の有機土木施工の
-
 【新年のご挨拶】代表理事 高田宏臣より
皆様こんにちは。地球守·有機土木協会の高田です。新年のご挨拶が遅くなりまして大変すいません。今年もどうぞよろし
【新年のご挨拶】代表理事 高田宏臣より
皆様こんにちは。地球守·有機土木協会の高田です。新年のご挨拶が遅くなりまして大変すいません。今年もどうぞよろし
-
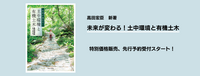 高田宏臣新著『未来が変わる! 土中環境と有機土木』先行予約のご案内
代表理事・高田宏臣の新著『未来が変わる! 土中環境と有機土木』(パルコ出版)が、いよいよ2026年3月2日より
高田宏臣新著『未来が変わる! 土中環境と有機土木』先行予約のご案内
代表理事・高田宏臣の新著『未来が変わる! 土中環境と有機土木』(パルコ出版)が、いよいよ2026年3月2日より
